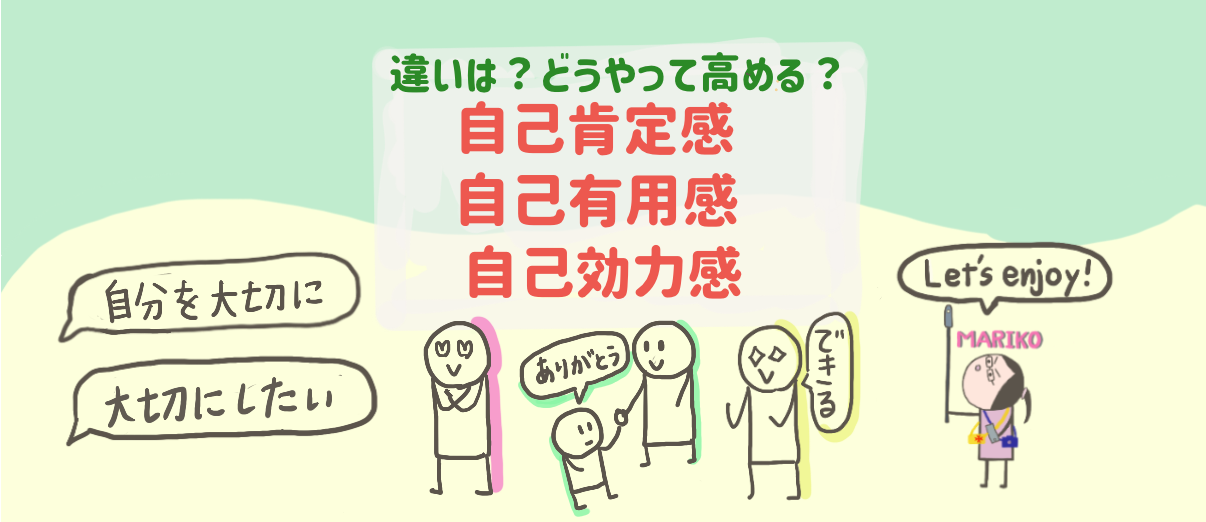自己肯定感・自己有用感・自己効力感の違いとそれぞれの高め方
自己肯定感・自己有用感・自己効力感という言葉は、よく似ているようで違います。
今、大人も子供たちも、自己肯定感が低い人が多いように思いますが、ある学校の先生から実は自己肯定感だけではなく、自己効力感や自己有用感を引き出すことが大切と聞きました。
その違いとそれぞれを高める方法をご紹介します。
スポンサーリンク
もくじ
自己肯定感/自己効力感/自己有用感の意味と違いは?
それぞれの意味と違いをご紹介します。
自己肯定感とは??
一番よく聞く、自己肯定感とは、
自分のあり方を積極的に評価できる感情、自らの価値や存在意義を肯定できる感情などを意味する語。自己否定の感情と対をなす感情とされる。
ここで押さえておきたいのは、自分自身がここにいていい、自分には価値のある人間であると自分で思えることなのです。
なので、何もしなくても愛されるし、ただいるだけでいいと思える感情のことです。
自尊感情に近い意味です。
自己効力感とは?
自己効力感 (じここうりょくかん)(self-efficacy) とは、自分がある状況において必要な行動をうまく遂行できるかという可能性の認知。
つまり、これは『自分はできる!』という気持ちを持てるということです。
人前でうまく話せる!絵を上手く描ける!など、自分自身は上手くできる!と信じられることです。
自己有用感とは?
自己有用感とは「自分の属する集団の中で、自分がどれだけ大切な存在であるかということを 自分自身で認識すること」です。自己有用感は自分に自信を高め、安易に問題行動に走ることを 抑止したり、危険なものに近づくことを抑制したりする働きをもちます。
つまり、自分が人に役にたっている!という感覚を人との関わりの中で感じること。
ただの存在としてというよりかは、家族の中や、クラスの中などの居場所で、自分が必要とされ、大切な存在であるとその人自身が感じることです。
自己肯定感/自己効力感/自己有用感の高め方
あなた自身、または、考えてあげたい相手の自己肯定感、自己効力感、自己有用感の中で一番低いと思いますか。
まずはご自身のことを感じてみましょう。その上で、周りの人との関係でも引き出す方法を考えてみましょう。
自己肯定感が一番根底にある自分そのものの存在を認めること、自己効力感や自己有用感は何か行動することによって、高めることができます。
自分自身で高める方法と、周りの人がアプローチする、それぞれの高め方のポイントをご紹介します。
自己肯定感の高め方
自己肯定感の低い人は、
・自分が嫌い
・自分なんていない方がいい
のようなことを思っていることが多いです。
自己肯定感を高めるには、何もしていない状態でも、何もできていなくても、「いいんだよ」「今日もよく頑張ったね」と自分で褒めましょう。
物理的に自分で自分のことをバグするのもおすすめです。
周りの人からは、シンプルにハグしてあげたり、何かしていなくても愛情をそのまま表現しましょう。
いてくれて嬉しいよ。と伝えるのもいいです。
人から認められることも大切ですが、それだけだと、一人になった時に自分なんて、、となるので、自分で自分を何もなくても褒める習慣をつけましょう。
自己効力感の高め方
自己効力感の低い人は、
・私なんて、何もできない
・大したことはできない
と言う人が多いと思います。
完璧主義な人が多い気がしますが、少しできていたとしてもできていないと思い込んでいることが多いです。
これも自分で自分のできることを探す習慣を作ってみましょう。
できないと思う人は、目標を高く持ってしまいがちです。
かなり小さい目標をたくさんつくり、それをできたできたと自分自身を褒めていくようにしましょう。
周りの人は、ちょっとのことでもできたことをすごい!と伝えましょう。
ただ、こんなんで褒められても。と思いがちなので、本当にすごいと思うことを説明付きでするのがおすすめです。
自己有用感の高め方
自己有用感だけは、必ず人との関わりが必要です。
・私なんて役に立たない
・ここにいても価値がない
と思いがちです。
自分から、人の役に立つことをやってみましょう。
・何か家のことを手伝っておうちの人に喜んでもらえた
・クラスの友達に何かを教えて喜んでもらえた
・道で困っている人を助けて喜んでもらえた
この、小さな一つ一つの自分が選んだ行動で、“ありがとう“ “助かった“と言ってもらえるのは最高に嬉しいコトバです。
反対に、子育て中の方や、子どもたちに関わる大人の人には、子どもたちに小さなお願いして、たくさんのありがとうや助かったを言うようにしてみてください。
全部できなくても、ちょっとでもしてもらって、ありがとう!って場面を作ることが、自己有用感を育むひとつです。
スポンサーリンク
まとめ
自己肯定感・自己効力感・自己有用感は、相手からみたら、目に見えないですし、高まっているのかもわかりにくい部分です。
ですが、この見えない部分が、次の行動に大きな影響があります。
子どもたちであれば、学習への意欲も変わってきます。
ぜひ、ご自身も、周りの人の見えない部分も大切にする時間を増やしてみてください。